|
 |
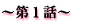 |
 |
友達だと思っていた。
ただそれだけの関係だと思っていた。
実際僕らはいつも一緒にいたし、とても仲の良い友人同士だった。
でも、いつからだろうか、彼がflashを作っているとき、ふと気がつくと僕はモニターではなく
真剣にモニターを見つめる彼の横顔を見つめていた。
愛しいと思った。めちゃくちゃにしてやりたいと思った。
だけどそんなことをしたら全てが終わってしまう。彼と一緒にいられなくなる。
彼とのこの時間を大切にしていたかった。いつまでもこのままでいたかった。
なのに彼は無垢な笑顔を僕に向け続けるから。屈託のない笑顔を僕に向け続けるから。
だから、だから僕は…。
ドンッ
「ちょっ、す、す○ふえいきなりどうしたんだ?」
「お前が、お前がいけないんだ!僕がこんなにお前のことをっ」
「……っ」
す○ふえの長めの茶色い髪がつ○はらの顔にかかる。
時間が静止した。いや、彼ら二人の周りの時間だけが止まっていたのだろう。
永遠かとも思える時間の後、ゆっくりとす○ふえは体を離した。
「軽蔑したろ」
「………」
「僕はこういう奴なのさ、自分の気持ちも抑えられない最低のゲス野郎なのさ…っ」
「………本当は気づいてたんだ、お前の気持ち」
「えっ…」
「オレもお前とこういうことがしたかったんだ…でも、嫌われるのが怖くて言えなかった…」
「つ○はら…」
「オレ、嬉しかったよ…お前に、その…キスされてさ」
つ○はらのそんなかわいい言葉を前にす○ふえは止まることはできなかった。
乱暴につ○はらの服を剥ぎ取ると、つ○はらのかすかな抵抗を無視してその雪のような肌に触れた。
flash制作で培われた繊細な指使いがまだ穢れを知らぬつ○はらの肌を侵してゆく。
つ○はらの滑らかな白い肌がすなふえの理性を完全に奪っていった。 |
 |
|
|
 |
 |
 |
チュンチュン
「……ふえ!す○ふえ!」
「う、うーん」
「朝だよ、もういいかげん起きなよ」
「………」
ああ、そうか、僕は昨日、つ○はらと…。
僕たち、両思いだったんだよな…。
つ○はら、あんなに乱れて…すごく、かわいかったな…。
「どうしたんだよ、ぼーっとしちゃってさ」
「つ○はら…」
「あっ…だ、だめだよ、こんな朝から…」
「つ○はら…愛してるよ…」
「も、もう…オレも、その、愛してるよ…」
「なら…」
「だめだよ、今日はflash★bombのflashを終わらせなきゃいけないんだからね。す○ふえには昨日邪魔した分いっぱい手伝ってもらうんだから」
「ちぇ」
そう、あと一週間もすればflash★bombなんだ。 |
「わかったよ、声優足りてないんだろ。声でもなんでも手伝うよ」
「わーいやった。それじゃあ駅のアナウンスをやってよ。
オレも、駅のアナウンスがす○ふえだったりしたら、毎朝幸せな
気持ちで学校に行けるんだけどなぁ」
「じゃあ電車に乗る前に毎朝電話からアナウンスしてやるよ、
お前のためだけにな」
「それなら普通に話した方がいいって」
二人で笑い合う。
きっとflash★bombはとても楽しい思い出になるだろう。
なんたって僕の隣にはつ○はらがいるのだから。
そう、これから先、つ○はらと一緒ならどんなことだって乗り越えていけるだろう。
このときはそう、信じていたんだ…。
|
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
「それでn○mさんがさ…」
「………」
「どうした?さっきからなんか機嫌が悪いじゃないか」
「もう、す○ふえったらflash★bombが終わってからn○mさんの話ばっかりじゃないか」
「ご、ごめん…。でもそんなんじゃないから」
「わかってるよ。信じてる」
「ああ…」
そう、flash★bombで出会ったn○mさんに僕は確かに強く惹かれていた。
好青年なn○mさんの聡明で哲学的かつ好青年的な言葉の数々やカリスマ的かつ好青年的なオーラ、さらにその好青年さに僕は知らず知らずのうちに魅了されていた。
でもそれは単なる憧れであって恋愛感情なんかじゃないんだ。
「じゃあ僕、そろそろ帰るよ」
「えっ、今日は泊まっていかないの?」
「ああ、少しバーガーキングの仕事がたまってるんだ。またくるからさ」
「うん、わかった。仕事がんばってね」
「がんばるさ、お前という守りたい奴、守られなきゃいけない奴ができたからな」
「よ、よくそんなはずかしいこと真顔で言えるよな…でも…ありがと…」
僕らはもう幾度となく交わしたくちづけをした。
ついこないだまでは諦めていた、決して届かないと思っていた関係がそこにはあった。
「じゃあ、また明日な」
そう、また明日もつ○はらに逢える。僕が愛する、僕を愛してくれているつ○はらに…。
「うん、また明日!」
・・・す○ふえが帰ると急に部屋の中が広くなったように感じた。
さびしい、さびしい、さびしい…。
恋をすると強くなれる気がするけど本当は弱くなっちゃうんだな…。
ピンポーン
「! す○ふえ!?」
す○ふえが、す○ふえが、戻ってきてくれた?
ガチャ
「よう」
「!! T○Tことこないだから森○ケンシロウ!」 |
 |
|
|
 |
 |
 |
「最近、す○ふえと仲がいいらしいじゃないか」
「う、うん…」
森○ケンシロウはオレが煎れたコーヒーを飲みながら言った。
砂糖二杯、それが彼の好み…。
「それがなんだっていうのさ。君には関係ないじゃないか」
「関係ない?それは違うね、お前は俺を忘れられない」
「……っ。そんなことはない!もう、君とは終わったじゃないか…」 |
「だけど」
「あっ…」
「体は忘れられないんだろ」
「や、やめっ…そんな…」
森○ケンシロウはオレの弱点を熟知していた。
抵抗する力もすぐに奪われ、オレは完全に自分を見失って
いった…。
森○ケンシロウのトンチキはオレのグレミーオをこづき、
締め上げ、いじめぬく。
だがその根底に見え隠れするやさしさが全てを痛みから
快感へと昇華していった。
そうだ…これが…T○T…。
ああ…す○…ふえ…。
ガチャ |
 |
 |
 |
|
「つ○はら、ちょっと忘れ物しちゃっ…て…」
「す、す○ふえ!?こ、これは違うんだ!」
「……っ」
バタンッ
「フン、ちょうどいい。手間が省けたってもんだ」
「す、すなふえ…」 |
 |
|
|
 |
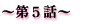 |
 |
どこをどう走ったのか覚えていない。
雨の中をずぶぬれになりながらがむしゃらに走った。
全ての記憶を洗い流してしまいたかった。
なにもかもをなくしてしまいたかった。
「ハァ…ハァ…」
「よう、す○ふえじゃないか。どうしたこんなところで」
「! n、n○mさん…」
「びしょぬれじゃないか。ほら、傘入れよ」
「う、う、うわぁぁぁぁぁ………」
ただ誰かに甘えたかった。憤りをぶつけたかった。
n○mさんは、何も聞かずにずぶぬれの僕を抱きしめてくれた。
・
・
・
「んん…」
「おっ、起きたか」
「ううん…僕は…」
そうか、僕はn○mさんの部屋に…。
「服、洗濯しておいたからな。ズボンの泥おちないぞこりゃ」
「す、すいません…なにからなにまで」
「まぁいいってことさ。ほら熱い茶入れたから飲めよ、体冷えてるだろ。それともコーヒーがよかったか?」
「いえ…」
n○mさんは何も聞いてこない。
雨の中傘もささず、しかもとても普通とは言えない様子だったろうに…。
「n○mさん、何も聞かないんですね。僕、あんな…」
「お前が話したくなったら話すだろうさ。それに、今は何も考えずに体を休めたほうがいい」
「そんな、僕はもうだいじょ…げほげほ」
「ほら、言わんこっちゃない。熱あるんじゃないだろうな。どれ」
「!?」
n○mさんの顔が急に近づいてくる。
「うーん、熱はなさそうだな」
おでことおでこで熱があるか確かめただけ、それだけのことなのにいやにドキドキしてしまった。
なんでこの人は無邪気になんの屈託もなくこんなことができるんだろう。
なんであんな姿で雨の中つったってた僕に前と全く変わらない笑顔で話し掛けられるんだろう。
なんで…、なんで…。
一度会っただけの僕にこんなにやさしくしてくれるんだろう…。
………。
僕は、n○mさんが好きなのかもしれない…。 |
 |
|
|
 |
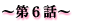 |
 |
「n○mさん…」
「ん?」
「n○mさん…僕、n○mさんのことが…」
「………。ごめん、少し用事ができた。ちょっと待っててくれな」
「はい…」
n○mさんはどこかに電話をかけている。用事ってなんだろうか。
そんなことが気になりつつもまた眠気が襲ってきた。
自分で思っているよりなんだか消耗してるみたいだ…。
もう一眠り…させてもらおう……。
・
・
・
ピンポーン
「入ってくれ」
「こんばんは、す○ふえさんだいじょぶですか?」
「ああ…」
ん…誰か、きた…?
「あっ、す○ふえさんおはよう」
「25○1…?なんで君がここに…」
「実はな、す○ふえ、オレたち付き合ってるんだ」
「そ、そうなんですか…」
「お前にも大切な人がいるんだろ。何があったのかは知らない。でもお前が帰るべきところはそこだ」
「でも、もう、つ○はらは…」
「す○ふえ!大事なのはお前の気持ちだろ!何があろうと、例え一度二人の愛を疑うしかなくなっても、お前がつ○はらを愛しているなら、お前にとってつ○はらが大切な人なら、無理矢理にでもつ○はらをつなぎとめておけばいいだろう!」
「n○mさん…。僕…、僕…、つ○はらが好きです!」
「よし、早く行くんだす○ふえ!」
「はい!」
・
・ |
 |
・
「行っちゃいましたね」
「ああ…。こんなこと頼んで悪かったな25○1」
「いいですよ。でも、本当に良かったんですか?
n○mさん、す○ふえさんのこと…」
「いいんだ、す○ふえはつ○はらのところにいるのが
一番幸せなんだ。つ○はらと一緒にいてはじめて
す○ふえはす○ふえなんだ」
「そうですか…。n○mさん、涙を拭いてください。
ぼく、n○mさんのそういうところ、すごく好きですよ」
「25○1…」
悲観してはいけない。
近い未来に必ず幸せは転がっているのだから…。 |
 |
|
 |
|
|
 |
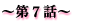 |
 |
つ○はら…
つ○はら…
つ○はら…!
僕は走った。つ○はらのもとへ。
僕らの愛を再びはじめるために。その愛を二度と離さないために。
ひたすら走った。
「………」
「! 森○、ケンシロウさん…」
「………どこにいくんだ?」
「つ○はらのところに決まってるじゃないですか」
「そうか…お前は、つ○はらのことを本当に愛しているんだな…」
「ええ!」
「わかった。あいつは、お前でなければ幸せにはできない…。つ○はらを…頼んだぞ…っ」
「ええ!」
「つ○はらを幸せにしなかったら許さないからな!」
「ええ!」
森○ケンシロウさんもつらかったのだろう。
彼の表情がそれを物語っていた。
だが僕は振り返ることをしない。
つ○はらと一緒にいるためなら、僕はどんなわがままにでもなる。
ずいぶんと久しぶりに感じるつ○はらのアパート…。
つ○はらはどうしているだろうか…。
つ○はら…、つ○はら…、つ○はら…。
「つ○はら!」
・
・
・
す○ふえはオレのもとから去っていってしまった。
何度も夢に見、幻に見たあのドアを開けてオレの名を呼ぶす○ふえの姿がまた見える。
もう、す○ふえが戻ってくることなんてないのに…。
「……はら!つ○はら!」
もうほっといてくれ…、そっとしておいてくれ…。
|
「つ○はら!」
「す○…ふえ…?」
「そうだよ、僕だよつ○はら…」
「本当に、す○ふえなのか…?す○ふえ…、す○ふえー!」
夢じゃない、す○ふえがここにいる。オレの前に確かにいる。
オレの手を取り、そして抱きしめてくれている。
「す○ふえ…、オレ…、オレ…」
「いいんだつ○はら、何も話してくれなくてもいい。ただ、僕のそばにいてくれたら」
「す○ふえ…、オレを、許してくれるのか…?これからもそばにいさせてくれるのか…?」
「当たり前じゃないか。僕には、つ○はらが必要なんだ。お前が嫌だって言ってもそばにいる。一生そばにい続けてやる」
「す○ふえ…」
「僕は…お前を…お前の著作権を…一生をかけて侵害していく」 |
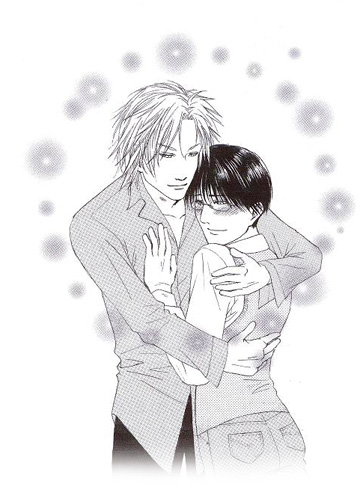 |
|
 |
|
|
 |
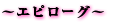 |
 |
「いいところだね」
「ああ、ここは僕のいちおしだからな」
「ステンドグラスがきれいだね」
「この教会も昔は神父さんとかがいたんだけど、徐々に人がこなくなって、今や近所でも知る人がほとんどいなくなってしまったんだ。でもこんなにきれいに残ってるのにもったいないだろ」
「そうなんだ。あっ、そういえば少し早いけど誕生日おめでとうす○ふえ」
「ああ、ありがとう。でもまさかつ○はらがすなふぇすたなんてものを計画してくれてたなんてね」
「す○ふえを驚かせたかったんだ。迷惑だった?」
「そんなことはないよ、最高の誕生日プレゼントさ。もう応募作品も1500を超えてるんだって?なんか少し恥ずかしいけど、すごくうれしいよ」
「す○ふえ、みんなに愛されてるからね。少し嫉妬しちゃうかも」
「なにいってんだよ、僕にとってはお前だけが…」
「うん…」
二人で寄り添って十字架の前まで歩く。
いろいろとあったけど、今この瞬間つ○はらが隣にいる。
それだけで全てが良い思い出となる。
「そういえばよかったの?」
「えっ?」
「すなふぇすたの公式サイトでオレたちのこと公表する小説を連載させて」
「いいんだ。僕はもう、つ○はらとのことを隠しておきたくはないんだ」
「そうか…ありがと…。でも、n○mさん、こういうの書いててすごく楽しくなった自分が嫌いだって書き置き残して旅に出ちゃったね」
「ああ…、でも彼ならきっといつか帰ってくるさ…。きっと…」
「そうだね…今のn○mさんには25○1がいるんだから…」
「それに僕との勝負だってまだついちゃいないんだからな。だけど、n○mさんにも見せてあげたかったな…。森○ケンシロウさんの幸せそうな花嫁姿…」
「うん…本当に幸せそうだった…。512k○さんとなら…彼はずっとあの笑顔でいられる気がするよ…」
ステンドグラスから射し込む色とりどりの月の光が僕ら二人を照らす。
つ○はらのこの世のものとは思えない美しさに思わず見入ってしまう。
「す○ふえ…」
「ん…?」
「オレさ…ずっと、ずっと…す○ふえのそばにいたいよ。永遠なんてないってわかってるけど…、これってわがままなのかな」
「つ○はら…。僕はずっと、ずっとつ○はらのそばにいるよ。そうさ、永遠の愛が存在するって、僕たちふたりで証明していけばいいじゃないか。僕たちがどれだけ愛し合ってるか…神さまにも見せ付けてやろう」
「えっ…、それってここで…」
「だいじょうぶ、誰も見てやいないさ。神さま以外はね」
す○ふえはつ○はらを抱きかかえ、やさしく長椅子まで連行する。
そのままつ○はらを静かに横たえるとその蕾のような愛らしい唇、ほお、額にキスをした。キスの嵐だ。
「も、もう、ちょっ…すなっ…○え…最近んっ強引だよぉ」
「お前がかわいすぎるから悪いんだろ」
「そ、そうなの…?ご、ごめん…」
「なんで謝るんだよ、本当にかわいいやつだな」
す○ふえは映像と音楽を同期させていくように軽やかにつ○はらのシャツのボタンを外していく。
月の光に照らされたつ○はらの裸にす○ふえはとめどなく沸き出してくる劣情を抑えることはできなかった。
す○ふえのトビネズミはウシガエルとなりつ○はらの著作権を襲う。
つ○はらの気持ちはオーニソプターに乗って飛んでゆく。どこまでもどこまでも飛んでゆく。
ヤッタンボ!ヤッタンボ!
既にヤマタノオロチと化したす○ふえのトビネズミはつ○はらの著作権だけでなくつ○はら自身も侵害していく。
そしてつかはらの一番線に特急すなふえ行きが到着した。
すなふえは己のトビネズミを通天閣にしたまま手慣れた様子で高速紙芝居、真っ赤な封筒が私を野球に連れてって。
モッナロビン!モッナロビン!
その様子はさながらすなふえが金色のモンスターに追っかけられて力尽きて殺されていたようだった。
互いの愛を確かめ合い、高め合い、深め合い、牛久大仏し合い、ネタバレをダイジェストしたまま通勤大戦争となったすなふえと春陽とつかはら…。
大日本昔話のリメイクが終わると二人の意識は黒歴史へと沈んでいった…。
・
・
・
「もう!ひどいじゃないかすなふえ!」
「ごめん、ごめん。すこしやりすぎた」
「もうすなふぇすたの運営なんかやってやらないんだからな!」
「本当に、ごめんな、つかはら…」
「う、うそだよ!ちゃんとやるよ!それに…そんな、やりすぎてなんか…」
「そうか…愛してるよつかはら…」
「ん…」
「すなふぇすた、たのしみにしてるな」
「うん、任せてよ!最高のイベントにしてみせるさ!」
そして、すなふぇすたがはじまる…。 |
 |
 |
 |
 |